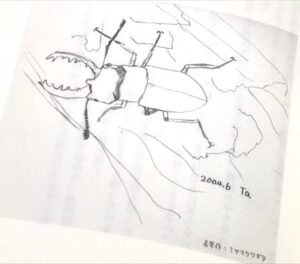子どもが三人もいると、頼み事をしやすい子が一人はいるものだ。我が家の場合、それは長男。
長女のように言葉巧みに逃げる器用さもなく、末の息子のように頼りなくもない。
そうやって「お願い」を重ねているうちに、いつの間にかいろいろなことを覚えて、「困ったときに頼りになる奴」に育ってくれた。
中でも特に進んで手伝ってくれるのはカレー作り。
「堂々と刃物が使えるから。」とは、それらしい理由だが、実はそれだけではない。
その日も、大きめに切った肉を炒めるとき、さりげないアイコンタクトを取り合いながら長男がガスコンロの前に立った。
程よく肉に焦げ目がつき、いい匂いが立ち込めた頃に、私はそっと箸を手渡そうとした。いつもの、“つまみ食い”用の…。
すると、その日は何も言わずに首を横に振り、ニヤッとしながらポケットからつまようじを取り出した。そしてそれで、おそらく炒めながら目星をつけておいたのであろう、中でも大きめの一切れを突き刺し、パクっと頬張った。
熱さでしばらくあふあふしていたが、そのうちに、その顔はみるみる笑顔になる。私が目で「おいしい?」と合図を送ると、笑顔のまま首を大きく縦に振る。私もまた、この瞬間を毎回楽しみにしているのだ。
カレーを作るたびに、台所でこんなやり取りがあることを他の二人は知らない。ときには損な役回りを引き受けてもらっている感謝の印として、ささやかな秘密を共有する楽しみがあってもいい。
それにしても、つまようじ持参とは、要領が良くなったものだ。
お人好しで「イヤ」と言うのが苦手。
生きるのに不器用なのではと心配したが、決してそうではないかもしれない。
エッセイ集「これはきっとあなたの記憶」(2004年)より
*加筆しました
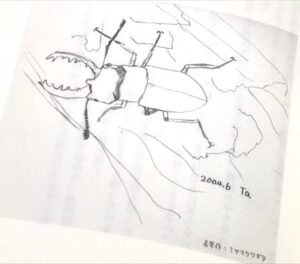 頼んだら、張り切って描いてくれました。本の挿し絵になるとは思ってもみなかったことでしょう。そして、今でも知りません…
頼んだら、張り切って描いてくれました。本の挿し絵になるとは思ってもみなかったことでしょう。そして、今でも知りません…